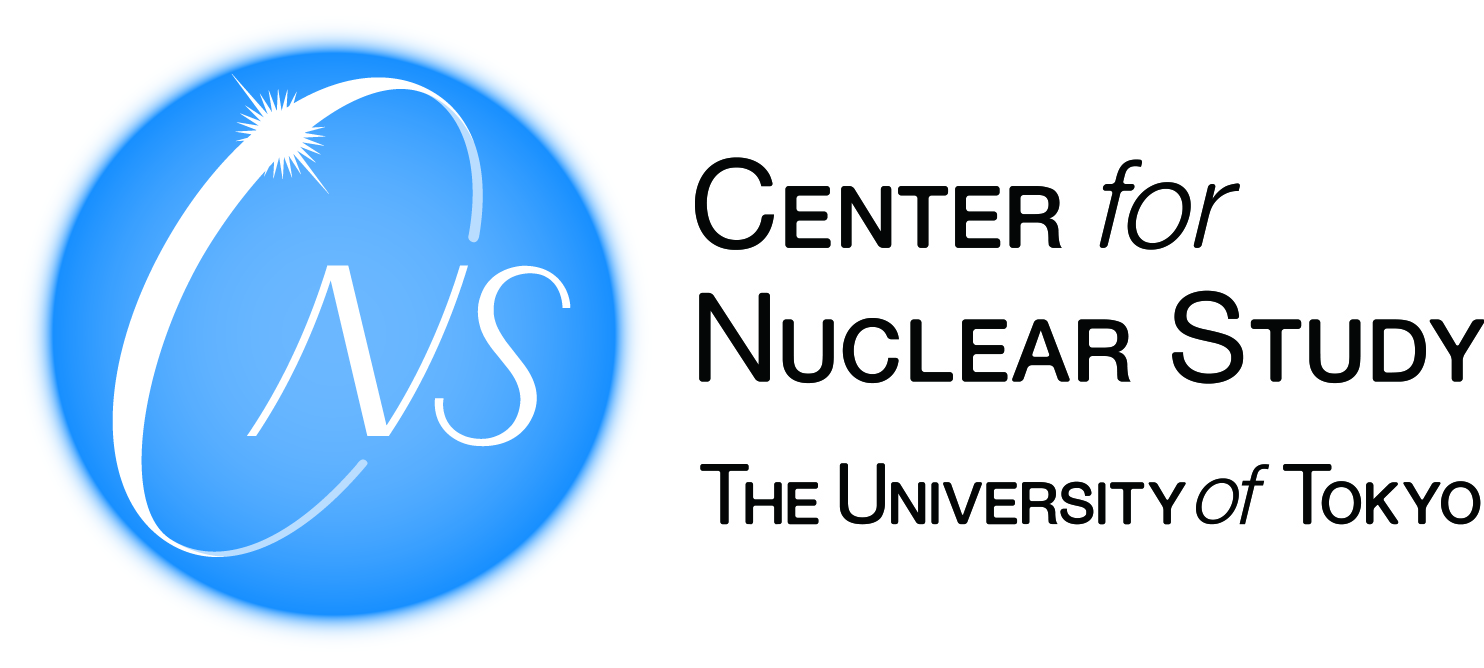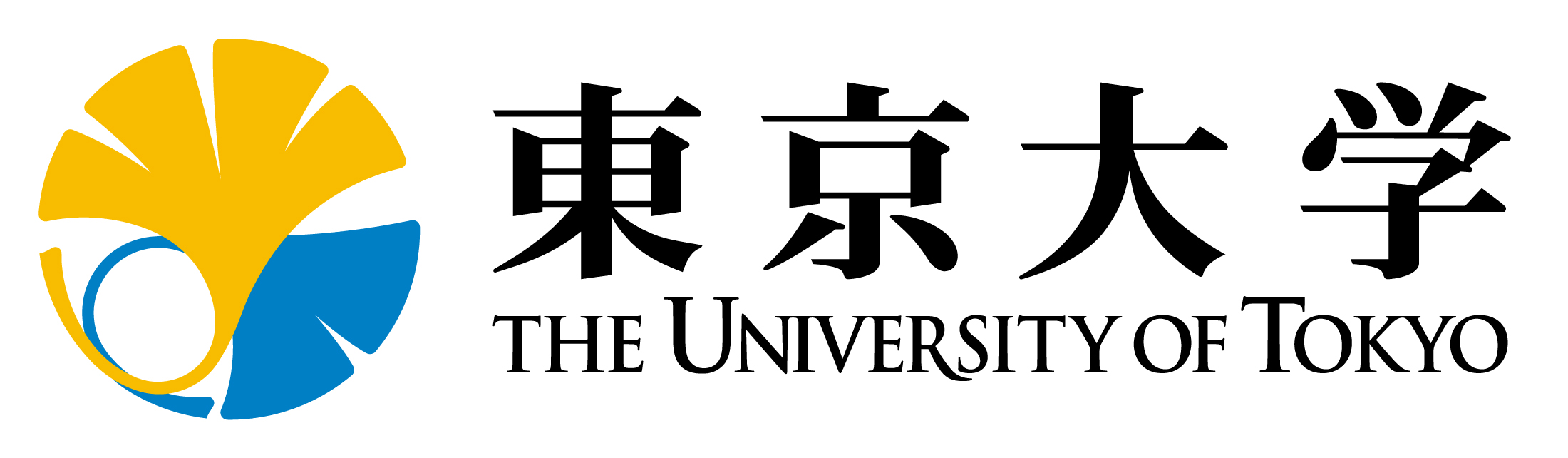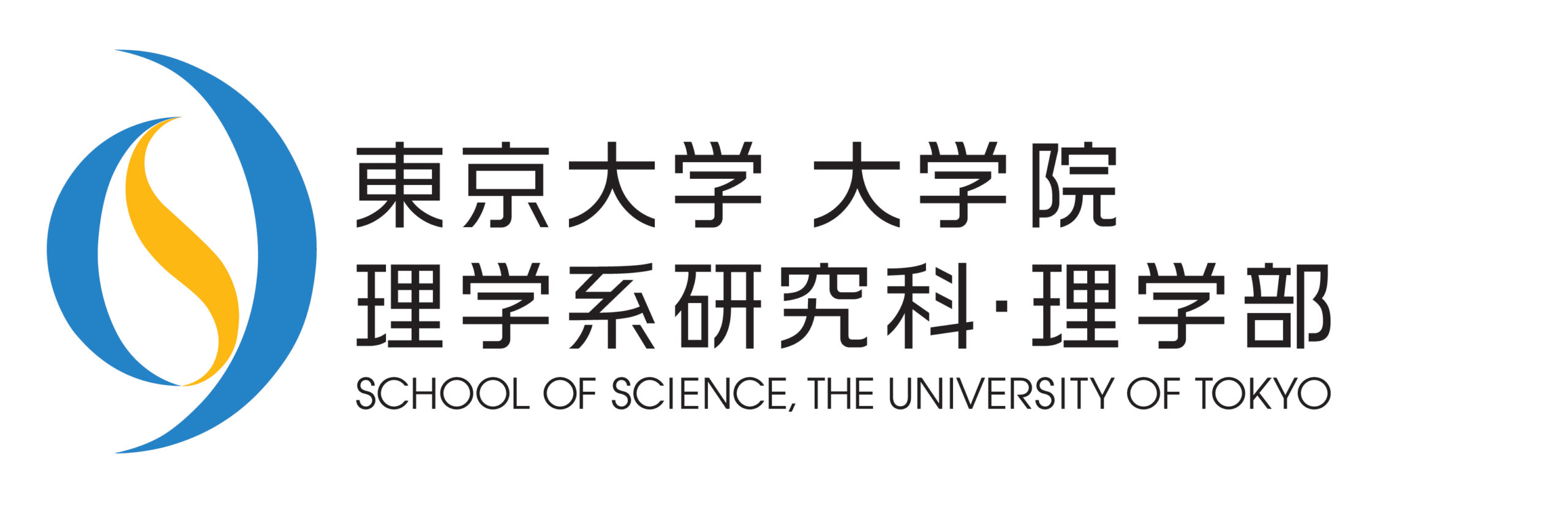核構造・
ダイナミクス
核構造研究
原子核は陽子数や中性子数が変化させた時に、従来の常識を覆す現象が発現します。 自然に安定に存在する原子核では、スピン軌道角運動量相互作用によって作られる秩序が 陽子数や中性子数がアンバランスな原子核では、テンソル力や、四重極相関が働き、秩序の様相が変わってきます。最近では、変形球形の形状相転移といった現象も報告されてきました。 高精度の質量測定、インビームガンマ線核分光、陽子共鳴散乱等、様々なプローブを用いて、 多面的に、原子核を構成する秩序を司る物理に迫ります。(青井研究室、今井研究室)
ジルコニウム原子核での量子相転移
ジルコニウム(Zr: 原子番号40)の中性子過剰核では質量数が98から100に変化するときに、突然、基底状態の形状が球形からレモン形に量子相転移することが知られていました。近年CNS理論グループでは安定なジルコニウム原子核の励起状態に既にレモン形が存在し、それが質量数99で入れ替わるという、変形共存模型を提案しました。
変形共存状態は、原子核の形状を変えたときに複数の平均場真空が現れる状態です。量子相転移は、図のように平均場真空のエネルギーが変化することで生じます。ジルコニウム原子核では2つですが、3つの平均場真空状態が存在する原子核も発見されています。しかし、異なる平均場真空の性質はほとんど調べられていません。
異なる平均場真空を調べる手法として、我々のグループは陽子共鳴散乱からの崩壊をみる実験を提案しました。
その手法の原理実証とジルコニウム原子核での量子相転移現象の原因を明らかにするため、九州大学のタンデム加速器施設で96Zrの陽子共鳴散乱実験を行いました。その結果、異なるスピン・パリティで共鳴が観測され、異なる励起状態の形状を明らかにすることができました。この手法を用いることで、今後、さらに中性子過剰Zr同位体の性質について迫ることができると期待されます。


短寿命希少原子核の質量測定
原子核の質量は核力、クーロン力など、核子間に働くすべての相互作用の結果として決定される量で、したがって原子核のエネルギー状態を記述する最も基本的な物理量のひとつです。原子核の質量を直接実験的に決定し、それらの系統性(中性子数依存性・陽子数依存性など)を明らかにすることで、原子核のエネルギー構造の進化を理解することができます。理研の加速器から供給される非常に中性子過剰あるいは陽子過剰な原子核ビームと、我々のグループが所有する高分解能ビームラインおよびSHARAQ磁気分析を組み合わせることで、数ミリ秒程度で崩壊してしまうような短寿命な希少原子核の質量を測定する手法を開発しました。(装置開発も参照)
この手法を駆使し、未踏の領域における原子核の質量や核構造が明らかになってきています。


ツェプト秒ダイナミクス
理研で発見されたニホニウム278(278Nh:原子番号113, 寿命~2ミリ秒)に中性子を20個ほど追加すると、半減期が”年”を超える「安定の島」(island of stability)と呼ばれる原子核群が存在すると予言されています。安定の島にある原子核の発見は、発見自体が原子核の量子系としての安定性の理解に大きくインパクトを与える課題です。安定の島の生成のためには、安定核同士の核融合反応では中性子数が足りないため、中性子過剰な放射性同位体を利用する方法が一つの候補とされています。
重イオン同士の核融合反応を上手に利用するには、核分裂のほか、融合疎外と呼ばれる現象の理解が不可欠です。現在までの実験から、標的とビームの原子番号の積に指数関数的な依存性が存在すると考えられていますが、そのモデルの不定性は100倍程度広がっていました。
核ダイナミクス研究室 今井研では量子科学技術研究機構 HIMACでの大強度136Xeビームを用いて、ポロニウム(Po: 原子番号84)からネプツニウム(Np:原子番号93)を人口的に生成し、核融合反応における融合疎外を定量的に評価する研究を推進しています。


通称「モザイク検出器」を開発。
2025年理学部カレンダーの写真に選ばれました。
エキゾチック変形
原子核は、高校の教科書で見るような丸い形をして存在しているのでしょうか?実際の原子核は、構成する陽子・中性子間に働く様々な運動量的あるいはエネルギー的相関によって、対称性を破る色々な形状に自発的に変わっていきます。四重極変形では、 超変形状態、ハイパー変形状態があります。また八重極変形や、正四面体、直鎖状や、 トーラス型といったよりエキゾチックな変形も予言されています。このような球形からずれた変形状態が現れることは数個から数100個からなる核子系の「自己組織化」の現れとして理解されます。変形状態の探索により、破れた対称性がどのように回復し、集団運動が誘起されるのかを 調べます。 (青井研究室、今井研究室)

(引用:Frank, A., Jolie, J., Isacker, P.V. (2019). Symmetry in Nuclear Physics: The Shell Model. In: Symmetries in Atomic Nuclei. Springer Tracts in Modern Physics, vol 230. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21931-4_2)
集団運動
この原子核を原子核散乱を通して「突っつく」ことで回転・振動運動を引き起こすことが できます。この現象は原子核集団励起と呼ばれ、原子核の堅さをはじめとした基本的な性質 を反映するため、原子核物理学の中心的な研究対象になってきました。 エキゾチック核反応グループではRIBFの不安定核ビームなどを用いて、原子核の新しい様相 と集団性を生み出す相互作用の研究を進めます。 (矢向研究室)
二重ガモ・フテラー巨大共鳴の探索
テトラ中性子
恒星の最後の姿である中性子星はその名の通り、主に中性子から構成される「超巨大原子核」ともいえる天体です。地球上の物質では考えられない、想像を絶する極限現象が起こっています。地球上には存在しない、4つの中性子のみからなる原子番号“0”の原子核「テトラ中性子」を人工的に作り出すことで、中性子星の内部や、中性子の間に働く核力の奇妙な性質を知ることができます。我々のグループでは二重交換反応 (8He + 4He → 8Be + 4n)という手法を用いて、4中性子状態を“そっと”(核子の反跳無しで) 生成することに成功しました。この実験はCNSが主体となって建設したSHARAQ 磁気分析装置が重要な役割を担いました。その結果、4中性子の生成閾値近傍に共鳴的な事象を観測しました。従来の理論では説明できないこの共鳴は、中性子系の未知な多体効果を示唆しています。テトラ中性子の研究は「多中性子系の原子核物理学」という新たな研究領域を拓くものとしてさらなる進展が期待されます。
我々の実験結果を受けて2023年、4中性子の生成効率が高い「ノックアウト反応(8He + p → p + 4He + 4n)」による測定が理研のSAMURAI磁気分析装置で行われ,4n核の存在を高統計精度で確認し,半世紀に及ぶ「強く相関する4中性子」の謎を解決しました。さらに同年には、中性子3系に関する研究も東北大学 三木准教授らとの共同研究によってSHARAQを使って行われ、新たな知見を生み出し続けています。世界で初めて4中性子系の実験的知見を示したことで、CNSの下浦享東京大学名誉教授(現理化学研究所開拓本部 研究員)が「4中性子状態の実験的研究」の研究により仁科記念賞を授与されました。 (今井研究室/ 旧下浦研究室)