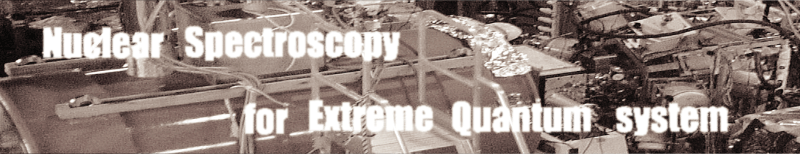- 東京大学大学院理学系研究科 附属原子核科学研究センター 教授
- 略歴 (ReaD 研究者情報
 )
)
- 1979 京都大学理学部卒業
- 1984 京都大学大学院理学研究科 博士課程 単位取得満期退学
- 1984-1988 京都大学 助手
- 1988-1992 東京大学 助手
- 1992-1994 立教大学 専任講師
- 1994-2000 立教大学 助教授
- 2000- 東京大学 教授 (現職)
- 委員歴、役員歴
- 1998-2000 日本物理学会会誌編集委員
- 1999-2000 大阪大学・核物理研究センター、B-PAC委員
- 2002-2003 大阪大学・核物理研究センター、P-PAC委員、(2003 委員長)
- 2005- 日本物理学会理事
- 2006-2008 日本工学会理事
- 2006-2008 大阪大学・核物理研究センター、P-PAC委員、(2007 B-PAC委員)
- 2008-2010 大阪大学・核物理研究センター、運営委員会委員
- 2008-2012 J-PARC PAC 委員
- 主な研究テーマ
- 中間エネルギー核反応を用いた安定線から離れた原子核の構造の研究
- 低エネルギー短寿命核ビームによる核反応
- セグメント型半導体検出器アレイの開発
- 高分解能磁気分析装置(SHARAQ)の開発
- 科研費
- 2007-2010 基盤研究(A) 代表 不安定核の二次核反応による中性子多体系の研究
- 2003-2006 基盤研究(A) 代表 中性子過剰核における殻構造の変化と集団性
- 1999-2001 基盤研究(B) 代表 安定線から離れた原子核の圧縮率の研究
- 1994-1995 重点研究 代表 陽子過剰核における陽子-陽子相関
- 1993 重点研究 代表 中性子過剰原子核のクラスター状態の探査
- 1992 奨励研究(A) 代表 クーロン励起を用いた不安定原子核の低励起状態の研究
- 研究概要
安定に存在する原子核に比べ陽子数と中性子数の比がアンバランスな原子核のエキゾチックな性質を、その原子核を二次ビームとした核反応実験により調べる。入射エネルギーや標的の種類に対応した原子核反応の選択則を駆使して、魔法数の変化や安定核では見られない励起モード、反応機構を解明する。
[ メンバー紹介のページに戻る|トップページに戻る]