ToStudents/labchoice のバックアップ(No.1)
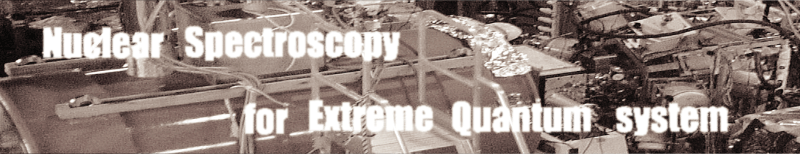
研究室の選び方このページは編集中です NUSPEQグループ博士課程4年の新倉です。このページを見ている学部生の方のために、研究室を選ぶときの参考になりそうなことを書いてみます。ここに書いてあることは、私個人の意見であり、一般的な話ではないことをはじめにお断りしておきます。 理学部物理学専攻で入ることの出来る研究室東京大学大学院物理学専攻では、理学部物理学専攻の研究室以外にもさまざまな研究室が大学院生を受け入れています。受け入れ教員一覧は以下のページで見ることが出来ます。 理学部物理学教室の研究室以外にも、大学院生のみを受け入れている研究室がかなりあります。我々極限原子核構造研究グループもその一つで、物理学専攻の中でも素粒子原子核実験、加速器(A2)サブグループに属していて、下浦教授と井手口講師がそれぞれ大学院生を受け入れています。A2サブグループだけでも、物理学教室以外に、原子核科学研究センター (CNS) ウェブページは参考程度に研究室を選ぶときには、おそらくはじめにインターネットでそれぞれの研究室のウェブサイトを見ると思います。しかし、我々のグループも含め、ウェブページの更新は大学院生やポスドクがボランティアで行っているところが多く、情報が必ずしも最新ではありません。ウェブにはメンバーと簡単な研究紹介しかない研究室が、非常におもしろい研究を行っている場合も多くあります。研究に忙しくてどうしてもウェブの更新が後回しになっていることも多いので、ウェブページは簡単な研究内容の把握と、メンバー構成、教員の連絡先を知る手段、程度に思っていてください。 研究室訪問のすすめというわけで、ウェブには載せていない最新の研究成果や研究室の雰囲気を知るためにも、 大学院進学の際は研究室訪問をすることを強くお薦めます。 どの研究室に行くかを全く決めていない状態でも、構わずにどんどん教員に予定を伺うメールをしてみてください。先生方はとても忙しいので出張や会議などで都合が付かない場合も多いですが、時間があれば必ず会ってくれます。そして、来る来ないにかかわらず歓迎してくれると思います。我々の研究室のように、近くに実験施設がある研究所の場合は、事前に連絡をしておけば、施設見学をすることも出来ます(加速器施設の場合、放射線管理区域の中にあるので、見学には事前の連絡が必要です)。 研究室選びのポイント研究室訪問の際には、修士や博士課程の大学院生がどのようなテーマで研究を行っているのか、実際に大学院に進学し研究室に入った場合に、どのような研究テーマで研究が出来るのかを聞くといいと思います。もちろん、興味のある研究テーマを自分で考えて提案し、それを指導教員にサポートしてもらうことも出来ます。研究室がその時点で特に集中して行っているプロジェクトがある場合、プロジェクトのなかでもどのような部分を任されるのか、誰が指導してくれるのか、などにも注目して話を聞くといいと思います。このようなことはウェブの載せて公開できないことも多いので、実際に会って話を聞くしかありません。 また、研究室のメンバー構成や雰囲気も重要です。指導教員の先生はとても忙しいことが多く、四六時中つきっきりで指導してくれることはほぼありません。定例ミーティングなどで重要な研究指針を議論する以外で、実際の作業に関すること(ソフトウェアの使い方や装置の動かし方など)は研究室の先輩や助教に教わることになります。訪問の際に、進学後は話をすることが多くなる先輩を紹介してもらい、話を聞かせてもらうといいと思います。教授は研究のいいことしか言いませんが、大学院生からならちょっとした裏話も聞けるかもしれません。 他大学の研究室 |