Physics のバックアップ(No.2)
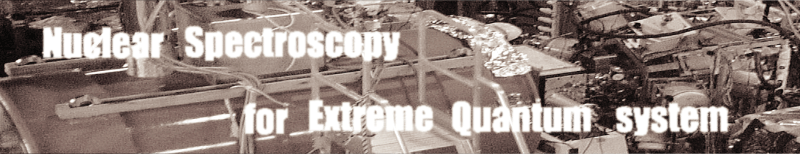
研究紹介概要近年の原子核物理実験技術の発展に伴い、原子核の研究はこれまでの安定核から不安定核へと、また低スピン状態から高スピン状態へと、大きくその研究領域が拡大してきました。そして、このような極端な条件下での原子核は、これまでの安定核には見られない特異な現象・状態がみられることがわかってきています。われわれの研究室では、インビームガンマ線分光という手法を用いた原子核の構造研究を通じて、有限多体量子系における性質について研究を行っています。 実験は下浦・井手口研究室のメンバーだけでなく、理化学研究所、東京大学、立教大学、京都大学、東北大学、原子力開発機構など他研究室、研究所との合同で20名ほどの共同研究として行うことが多いです。実験は一年で2-5回程度、1-10日程度で行います。実験を行う場所は我々の研究室が所属する原子核センターがある理化学研究所で行うことが多いですが、そのほか、東北大学サイクロトロン、原子力研究機構(東海村)、フィンランドのユバスキラ大学など、研究の目的に合わせ、さまざまな施設での実験を行っています。 研究テーマ紹介中間エネルギー核分光研究 (下浦研究室)下浦研究室では、おもに中間エネルギーの不安定核ビームを用いた実験を通じて、中性子過剰核での核構造の研究を行っています。
低エネルギー核分光研究 (井手口研究室)井手口研究室では、おもに低エネルギービームを用いた実験を通じ、原子核の高スピン状態の研究を行っています。
検出器の開発ガンマ線検出器アレイCNS-GRAPEの開発我々の研究室では、大型ガンマ線検出器の開発を行っています。この装置は特に、不安定核ビームを用いた逆反応によるガンマ線核分光研究において、高分解能、高検出効率を達成するための装置として開発が進められています。 CNS-GRAPEに関する詳細は、こちらのページをご覧ください。 SHARAQスペクトロメータ開発我々の研究室は、RIBFにおいて散乱粒子を高分解能で測定し、原子核の状態を鮮明に識別するための磁気分析装置SHARAQ の開発プロジェクトにも参加しています。SHARAQプロジェクトに関する詳細は、こちらのページ その他検出器、実験装置開発我々の研究室では、GRAPEやSHARAQといった大型検出器開発プロジェクトのほか、さまざまな検出器開発、運用を行っています。
用語解説うまいことリンクだけ取り込める方法がないのかな? 'にいくら/web/研究紹介/用語解説'には、下位層のページがありません。
|